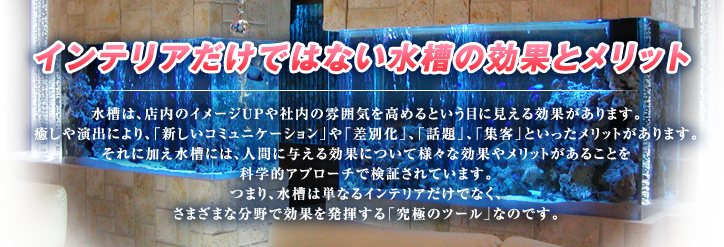パソコン作業(英文のタイピング)を行ってもらった多数の被験者に、観賞魚がいる空間といない空間とに分かれてもらい、体の変化を計測しました。

観賞魚を眺めている被験者の心拍変動を時間ごとに計測しました。

観賞魚は「人をリラックスさせる効果」が明らかになり、観賞魚を身近に置くことで、よりリラックスした生活を送ることができます。

パソコン作業(英文のタイピング)を行ってもらった多数の被験者に、
観賞魚がいる空間といない空間とに分かれてもらい、体の変化を計測しました。

水槽のある空間にいる被験者のストレス度合いを表す物質(唾液アミラーゼ)の計測と質問紙調査を行いました。

観賞魚がくつろぎをもたらし、ストレスを和らげる効果があることが明らかになりました。
観賞魚を部屋に置くことで、学校や会社などで受けるストレスを緩和できます。

高齢者施設に本物の水槽とモニターに映した疑似水槽を交互に設置し、その間の施設利用者の行動をビデオにより観察しました。

疑似水槽と本物の水槽を設置したときに、それぞれの状況下で被験者の行動を観察しました。

観賞魚の“好奇心を高める効果”が明らかになりました。観賞魚は高齢者の趣味としても最適で、生きがいにもつながっていきます。

金魚3匹が泳いでいる水槽を3種類のパターンで被験者に観察してもらいました。
■パターンA
ぼーっと水槽を観察してもらう。
■パターンB
水槽を見て、金魚の口パク(砂利を突っつく)回数をカウントしてもらう。
■パターンC
水槽を見て、金魚の口パク(砂利を突っつく)回数をカウントしてもらい、その回数を報告してもらう。

それぞれのパターンで被験者の脳がどういった変化をしているのかを測定しました。

目的を持って水槽を見ることで、脳内のヘモグロビン量が増加していることが明らかになった(赤色が強くなった)。
脳が活性している状態になっている。
特に後ろの脳(後頭葉)が活性しており、この部分は視覚情報を認識するために重要な役割を持っている。